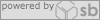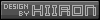2009/11/13 金 + お知らせです! +
宇根さん、という方が糸島の二丈町にいらっしゃいます。宇根豊さん。
「特定非営利活動法人 農と自然の研究所」代表理事、という肩書き。漢字おおいなー。福岡県の農業改良普及員から、新規就農、2001年より「農と自然の研究所」を立ち上げ、自然環境、特に虫や生物への暖かい目線で執筆、講演などもされています。
「農と自然の研究所」
http://hb7.seikyou.ne.jp/home/N-une/
農文協のサイトに、わかりやすく経歴が。
「農文協(食と農の応援団)うね ゆたか」
http://www.ruralnet.or.jp/ouen/meibo/022.html
んで、ニュースレターの文章にしみじみと感じ入るものがあったので、許可をいただき転載させていただきます。快くご許可を頂いた上に、テキストデータまで送っていただきました。宇根さん、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
「遠い仕事 知らない生産」 農と自然の研究所ニュースレター24号より転載。
以下、すべて著作権は宇根豊さんにあります。
「特定非営利活動法人 農と自然の研究所」代表理事、という肩書き。漢字おおいなー。福岡県の農業改良普及員から、新規就農、2001年より「農と自然の研究所」を立ち上げ、自然環境、特に虫や生物への暖かい目線で執筆、講演などもされています。
「農と自然の研究所」
http://hb7.seikyou.ne.jp/home/N-une/
農文協のサイトに、わかりやすく経歴が。
「農文協(食と農の応援団)うね ゆたか」
http://www.ruralnet.or.jp/ouen/meibo/022.html
んで、ニュースレターの文章にしみじみと感じ入るものがあったので、許可をいただき転載させていただきます。快くご許可を頂いた上に、テキストデータまで送っていただきました。宇根さん、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
「遠い仕事 知らない生産」 農と自然の研究所ニュースレター24号より転載。
以下、すべて著作権は宇根豊さんにあります。
日本的な「生物多様性」はあるのか
1、村外からの外来思想
「生物多様性」という概念は大好きだが、日本の百姓にとっては、これも外来の言葉であり、科学が生み出したものとして、またしても外から提供され村にやって来た。どうして、新しい言葉や思想は、外からやってくるのだろうか。「自然」も「風景」も、「生態系」も「多面的機能」も、輸入語だ。そのことを批判しているのではない。それに匹敵する思想は日本にはなかったのだろうか、と考えるのである。
もちろん、新しい思想が百姓から、しかも身近な村中から生まれる例はほとんどないだろう。どこからかもたらされるものが圧倒的に多い。それは悪いことではない。問題は、いつも同じ所から、同じ見方で、同じ考え方で生み出されて、村に降りてくることにある。それは「科学」を本拠地にして、しかも客観的な装いを凝らしながら、一つの価値観を植え付けてくる。「科学は普遍的で客観的ではないの?」と思っている人は、大きな誤解をしている。
科学は現在社会では最も説得力のある世の中の見方であるが、とても偏っている。だからこそ、鋭く深い見方ができるのであるが、欠点も大きい。それは「特徴」だと言い換えてもいい。
【特徴1】自分を世界から切り離して、外側から冷たく眺める。
【特徴2】時代の精神にとらわれる。
生物多様性という言葉は好きだが、この言葉を使うと、この考えに匹敵する日本的な「もの」から眼が離れていくような気がする。今回はこのことを考える。実はこのことを、先日のイオン財団と環境省の「第1回生物多様性アワード」の受賞スピーチで語ったので、再録し補足することにする。(「アワード」とは「賞」のことだ。また外来語か、と思う。)
2、情愛のふるさと、いきとしいけるものへのまなざし
婆ちゃんが畦草刈りを急に止めて、田んぼの下の道を通って、家に戻っていった。しばらくすると畦で線香を焚いて、手を合わせている。そして草刈り機を抱えて帰って行こうとする。そこで、「どうしたとね?」と尋ねてみた。「いや、シマヘビを切ってしまってね。もう今日は仕事はやめにする」「しかたなかよ。草刈り機じゃ気をつけていても、ついきってしまうもんね」と慰める。
ほんとうに百姓はおびただしい生きものの命を奪う仕事をしている。いちいち気にしていたら、身が持たない。田畑を耕せば草を枯らし、多くの生きものの生きる場を奪う。突然の代かきや中干し、落水、稲刈りにしても、生きものの命を奪う。この哀しみを婆ちゃんはしっかり受けとめて、引き受けている。私と言えば、いやその程度では絶滅することはない、それも生態系には織り込み済みで、中程度攪乱説にしたがえば、そういう百姓仕事つまり生態系の攪乱が生きものたちの遷移を止めて、安定に寄与しているのだ。その証拠に、また次の年になれば、同じように草は生え、虫は生まれるではないか、と自分に言い聞かせる。婆ちゃんに比べたら、薄っぺらな世界に住んでいる。こうした情念のふるさとと生物多様性とはどう結びつくのだろうか。
当然のことながら婆ちゃんは「生物多様性」などという考え方は知らない。しかし、生きものへの情愛は、私などよりもはるかに深い。現代人が支持する「生物多様性」は、自然という生きものの世界を外側から見ている。一方かつての日本人は、とくに百姓は、生きものを自分の世界の一員として、内側から見ていた。
3、自然と世界認識
友人の故・森清和の最期の言葉をよく思い出す。「自然は大好きだが、自然と言った途端に自然の外に出てしまうのが悲しい」これは自然と現代人の本質を見抜いている。明治時代の前半までは、日本人は「自然」(Nature)という言葉も概念も知らなかった。それまでは、自然はどう見えていたのだろうか。それがこの数年、ずっと気になっている。
私なりのたとえ話をしよう。池があるとする。池の中のフナには、池は見えない。ただ池の中の生きものや水や底の土、つまり池の中の世界はじつによくつかんでいた。池は、そこから岸をはい上がって、地上に出たときに見えるかもしれないが、フナはそんなことをしようとは思わない。
この池を「自然」だと思えばいい。かつての日本人は、池の中のフナであった。自然を知らなかったが、自然の中のことと十分知っていた。現代の日本人は、池を外から眺めているが、池の中に入ることが少なくなった。自然の中の生きものたちと一緒に過ごすことがなくなった。このことの不幸もまた、考えてみなければならない。「自然」を知らなかった先人たちは、私たちよりはるかに生きものを知っていた。
90歳を越える百姓への聞き取りでは、百姓は約600種の生きものの名前を呼んでいたそうだ。しかも名前を知っているだけではない。その生きものの生や自分との関係も深く身体に刻んでいる。現在では福岡県内の調査では、約150種である。科学は自然の外からの生きもの認識であるが、先人の百姓たちは自然の内側からの生きもの認識だった。現在とどう違うかと問われれば、まなざしと情愛の深さが違うと言うしかない。
4、「全種リスト」の新鮮さ
子どもたちが質問してくる。「いったい、田んぼにはどれくらいの生きものがいるの」自然観、世界認識の扉を開けたがっている。それなのに「そんなこと誰も知らないよ。研究もされていないよ」では、従来の狭い科学から一歩も出られない。
私たちが百姓や子どもたちにすすめている「生きもの調査」は、世界認識の方法でもあるのだ。その方法は二つある。まず、生きものに眼を合わせて、相手の名前を呼ぶことだ。距離は一挙に縮まり、情愛が芽生えてくる。かつて、
この「情愛」を仕事の中で、百姓は深めて来た。ただの虫にも多くの地方名があるのが、その名残だ。しかし、生きものへのまなざしは、農業の近代化で衰えてしまった。そのことに農学だけでなく「科学」は冷淡だ。
科学者だけが、専門分野で種や生態を知っておけば、論文にしておけば、私たち百姓や国民のまなざしの衰退など、ほとんどどうでもいいと思っているのではないか、と疑うことがしばしばだ。ここで科学は何のためにあるのだろうか、を論じる紙幅はないので、別の機会にするが、科学が内からのまなざしを棄てたことが、この冷淡さの原因になっていることは指摘しておきたい。
そこで、科学に依拠しながらも、世界に認識へのもうひとつのアプローチが、農と自然の研究所の桐谷委員会では、2009年2月に作成した「田んぼの生きものの全種リスト」であった。これは私が科学を重視している証拠でもある。これまで「全種リスト」がなかったのは、いつのまにか科学も外側からの「世界認識」の学である使命を忘れてきたからであろう。
この世の生きもの全種に命名しようとしたリンネ(1707〜1778年)の時代には、全種とは1万種ぐらいだと思われていたそうだから、現代では途方に暮れるのもわかる。せめて個々の分野のさらに狭い種類だけにしようと言うのもわかるが、それが「世界認識」の放棄になることを科学者は少しは自覚してほしい。
日本の農地では最も研究されている田んぼの生きものの全種リストがなかったのは、科学が現代社会を支配している価値観に寄り添っていることを証明している。時代が要請しないものをやる人間は危険人物だろう。田んぼの生きものの場合は「有用性」にとらわれてきた。したがって、有用性がないものを研究対象にならなかったし、まして「世界認識」など近代化農業は歯牙にもかけなかった。
ところが、「ただの虫」という世界が見つかり、「生物多様性」が輸入され、桐谷圭治さんによって「IBM」という農学史上初めて、世界認識への切り口が提案され、生きもの調査に取り組んだ百姓や子どもたちによって、「いったい、田んぼという世界にはどれくらいの生きものが生きているのだろうか」という世界認識への志向が「全種リスト」への要請となったのである。
農と自然の研究所が桐谷圭治さんに相談して、全種リストを作成したのは「生物多様性」「IBM」という自然の外側からの概念の中身を充填するためと、「ただの虫」「ただの草」の実態を明らかにするためだ。そして何よりも「有用なもの」以外の生きものへの伝統的な百姓のまなざし復権の土台としたかったからである。
田んぼの生きもの全種リスト(桐谷圭治編)
動物 2495種
原生生物 829種
昆虫 1748種
植物 2146種
クモ・ダニなど 141種
双子葉植物 1192種
両生類・爬虫類 59種
単子葉植物 501種
魚類・ 貝類 189種
裸子植物・シダ・コケ 248種
甲殻類など 45種
菌類 205種
線虫・ミミズなど 94種
総合計 5470種
鳥類 174種
ほ乳類 45種
5、「全種リスト」の限界
果たして全種を科学的に明らかにしたからと言って、ほんとうに世界認識になるのだろうか。それに、これが百姓の伝統的な生きものへのまなざしの復活にほんとうに寄与するのだろうか。何より、百姓はこの全種すべてを認識できない。科学者だってそうだろう。そうすると、だれが全種を認識するのだろうか。少なくとも人間界には誰もいないことになる。しかし「科学」では、認識できるような気になることができる。まるで「創造神」になったように。これが科学が発明した世界認識であろう。すごいと思う。だが、これだけでは困るのである。
私たちは「生物多様性」を、伝統的な文化、あるいは個人の体験で実感しているからこそ、案外違和感を抱かずに受け入れた。それは、(1)遺伝子レベルでの多様性や、(2)種レベルでの多様性や、(3)生態系レベルの多様性だけでなく、(4)情感レベルでの納得:生きものとのつきあいの経験=生きものに見とれ、生きものの死に涙する感性を土台にして、(5)文化レベルので無意識の受容:自然を外から見ることがなかった伝統的な自然観=生きものの一員だった日本人=一緒に生きてきた生きものたちへの情愛があったからであろう。
全種リストは、一つの条件付きで、その人の、その地域の、その国の生きものへのまなざしの「目録」にできる。その条件とは、この自然の外側からのリストと、自然の内側からのまなざしが出会う土俵ができるならば、という条件である。
6、ただの虫のとらえ方
その「土俵」の一つの実例を示してみよう。
「ただの虫」は虫見板によって、百姓によって発見された。害虫を覚え、益虫を覚えた百姓にとって、害虫でも、益虫でもない虫が気になってきたのだが、誰も知らないのだから仕方がない。「ただの虫だろう。放っておこう」と言い合っているうちに、新しい言葉と分類概念が誕生したのだ。
「ただの虫」は日本的な、生物多様性に先行した概念ではないか、という指摘はありがたいが、ただの虫は生物多様性に出会わなければ、外からの「世界認識」になることがなかった。なぜなら、ただの虫は害虫や益虫と区別する分類概念にとどまり、図のような自然の「世界認識」に育てることができなかった。ただの虫はなんのために田畑にいるのだろうか、とばかり考えてきたからだ。つまり、自然の内側からの認識の外に出ることがなかったからだ。私もこの図を書き始めた5年ほど前からただの虫はいったい何種類ぐらいだろうか、と考え始めたのだから。
今年も農と自然の研究所と環境稲作研究会合同での定例田んぼの生きもの調査で、毎月16箇所を回るが、9月になると、虫見板の上に「跳び虫」類が100〜300匹も落ちてくる。(田植直後から稲株にいることもわかった)2種が混在しているのは間違いがない。稲の枯れた下葉を食べているようだが、名前が未だにわからない、誰に聞いてもわからない。この程度にしか、田んぼのことはわかっていないのだ。
それを「わかりたい」という気持ちは、残念ながら科学的な接近からしかもたらされないようだ。しかし、科学が田んぼの跳び虫を放置しているのは、有用性がない(ほんとうはあるのに)からであるが、百姓の内側からの要請もないからでもある。つまり、百姓自身のまなざしの復活なしには、この全種リストを内と外の両側から響き合うリストにすることは不可能である。したがって、この全種リストは生きもの調査などの百姓の取組みがないところでは、科学者だけが、自分の専門領域だけを検討するデータベースになってしまうかもしれない。そうはしたくないのである。
このリストが、試験研究 田んぼの跳び虫の一種機関ではなく、農と自然の研究所という百姓たちのNPOによって作成された意味がここにある。
7、どちらの田んぼが豊かなのだろうか
ここで、思想的な問題を出してみよう。二つの田んぼがあるとする。
-Aの田は赤トンボが10アールに5000匹生まれているが、当の百姓はそのことを知らない。
-Bの田では赤トンボは100匹しか生まれていないが、耕作している百姓はそのことを気にしている。 さて、どちらの田んぼが豊かだろうか。
A:赤トンボが5000匹いる しかし百姓はそれを知らない
B:赤トンボが100匹しかいない 百姓はそのことを悩んでいる
私の結論は、「Bの田がいいに決まっている」である。ところが「生物多様性」という概念を知っている人は、「Aの方が生きものが多いでしょう」と反論するだろう。それは、すでに自然を外側から見ていることに気づいていない。
私の論拠は二つある。赤トンボを見つめる百姓のまなざしがなければ、5000匹いるかどうか、誰がわかるというのだろう。次に、生きものの種類や密度だけで、生物多様性の豊かさを量ろうとするのは、科学的なようだが、大きな危険性をはらんでいる。誤解を恐れずに言えば、生きものが大切なのではなく、生きものへのまなざしが大切なのだ。赤トンボが100匹しか生まれないことを木にしている百姓は、田んぼの生きものの世界を豊に内側からみるまなざしを持っている。Bの百姓は、池の中のフナにもなりきれる人間である。
8、「赤トンボが飛んでいる」という言葉の意味
「赤トンボが飛んでいる」と妻が言う。私は「何という種類か、何匹飛んでいたか」と問う。妻は「そんなことより、赤トンボが飛んでいたのよ」と言う。つい私は、科学的に対象の種や密度に関心を注ぐ。その瞬間にそれを見つめている人間のまなざしを忘れてしまう。じつは「赤トンボが飛んでいる」という発言は、赤トンボのことだけではなく、その赤トンボ見つめる本人のまなざしや、その赤トンボが飛んでいた時と場所つまり自分もそこにいた世界全体を語ろうとしているのに、赤トンボのことにしか興味を示さない社会になろうとしているのではないだろうか。
この前ね、田んぼに行ったらね、お父さんのまわりに、ほんとうにがいっぱい赤トンボが集まって飛んでいたね。お父さんが腰を伸ばしても、ぜんぜん逃げないんだね。「そりゃあ、お父さんがイケメンだからじゃないかな」それは絶対ないと思う。「お父さんの汗の臭いが好きなんだよ」やめてよ、吐きそうになる。
「それじゃあ、お父さんの近くに来ると、何かいいことがあるからだよ」うーん、そんな気がするけど、いったい何がいいことなんだろう。
あっ、わかった。お父さんが田んぼで仕事して動き回るから、お父さんの回りの虫が飛びはねるんだね。それを赤トンボは食べに集まってくるんだね。でも、お父さん、いい気持ちだね。」
そうなんだ。百姓って、そうなんだ。
9、生きもの調査の再評価
あなたにとって田んぼの生きもの調査を実施する意義は何ですか?
福岡県農のめぐみ地区 宮城県のグループ
意義 実数(人) 割合(%) 実数(人) 割合(%)
1.減農薬・有機農業の効果を確かめるため 50 29.6 19 20.7
2.農産物に付加価値をつけるため 4 2.4 15 16.3
3.環境支払いの支援金をもらうため 7 4.1 2 2.2
4.農業に対する見方や農政を変えるため 11 6.5 12 13.0
5.環境を守るため 43 25.4 −
6.地域のタカラモノさがし 5 3.0 −
7.家族や地域の子どものため 1 0.6 7 7.6
8.未来のため 6 3.6 14 15.2
9.生きものの名前や生態を知るため 15 8.9 12 13.0
10.自分の楽しみや勉強のため 6 3.6 11 12.0
11.その他 5 3.0 −
無効回答 16 9.5 −
小計 169 100.0 92 100.0
#福岡県では、一つだけ選択。宮城県では二つ選択。(2007年)
当初、私たちは「生きもの調査」を環境把握の「手段」だと位置づけようとしていた。ところが、調査自体が目的になってきたのには、驚いている。これはどうしてだろうか。「環境把握のための農業技術」が従来の技術論におさまりきれない証拠かもしれないが、「伝える」「表現する」新たな地平が開けてきているのではないだろうか。それは上のアンケート調査結果に見事に現れている。
これは私たちの体の中の二つの動機を見事に表している。私たちは9,10を土台にして、6,7,8という世界で暮らしている。そのことは、外部の人間には見えないし、説明する必要もない。しかし、それを説明しなければならない契機が生まれているからこそ、1,2,3、4という回答が出てくる。生きもの調査はこうした三層構造になっているのである。そしてもっぱら外部の人間から見ると、上層の1〜5が目立って見えるということなのである。
一番大切な世界は、9と10ではないか。これは内側からの、池の中のフナの視点であるからだ。
10、生物多様性を受け入れる土台
生物多様性に匹敵する日本的なものは存在しない。しかし、それよりももっと深い生きものへの情愛を込めたまなざしは豊かに存在してきた。こういうまなざしがないところでは生物多様性はただ自然の外側からの概念にとどまるだろう。いずれにしても科学の側から、一見科学的でない生物多様性という思想が生まれ落ちたのは、生きもの世界をとらえる科学の限界を超えようとする対案だった。そういう方向でこの考え方は育てて行きたい。一方の日本の伝統的な生きものへの情愛もずいぶん衰えてきた。このまなざしを復活させようとする試みが、「生きもの調査」であったし、今呼びかけている「生きもの語り」である。「生きもの指標」は生きもの語りのための方法でもある。
科学は人間の情感の上に咲かなければ、冷たいままだ。生物多様性もまた、私たちの生きものへの情感・情愛の土台の上に咲かせるしかない。
「生物多様性」という概念は大好きだが、日本の百姓にとっては、これも外来の言葉であり、科学が生み出したものとして、またしても外から提供され村にやって来た。どうして、新しい言葉や思想は、外からやってくるのだろうか。「自然」も「風景」も、「生態系」も「多面的機能」も、輸入語だ。そのことを批判しているのではない。それに匹敵する思想は日本にはなかったのだろうか、と考えるのである。
もちろん、新しい思想が百姓から、しかも身近な村中から生まれる例はほとんどないだろう。どこからかもたらされるものが圧倒的に多い。それは悪いことではない。問題は、いつも同じ所から、同じ見方で、同じ考え方で生み出されて、村に降りてくることにある。それは「科学」を本拠地にして、しかも客観的な装いを凝らしながら、一つの価値観を植え付けてくる。「科学は普遍的で客観的ではないの?」と思っている人は、大きな誤解をしている。
科学は現在社会では最も説得力のある世の中の見方であるが、とても偏っている。だからこそ、鋭く深い見方ができるのであるが、欠点も大きい。それは「特徴」だと言い換えてもいい。
【特徴1】自分を世界から切り離して、外側から冷たく眺める。
【特徴2】時代の精神にとらわれる。
生物多様性という言葉は好きだが、この言葉を使うと、この考えに匹敵する日本的な「もの」から眼が離れていくような気がする。今回はこのことを考える。実はこのことを、先日のイオン財団と環境省の「第1回生物多様性アワード」の受賞スピーチで語ったので、再録し補足することにする。(「アワード」とは「賞」のことだ。また外来語か、と思う。)
婆ちゃんが畦草刈りを急に止めて、田んぼの下の道を通って、家に戻っていった。しばらくすると畦で線香を焚いて、手を合わせている。そして草刈り機を抱えて帰って行こうとする。そこで、「どうしたとね?」と尋ねてみた。「いや、シマヘビを切ってしまってね。もう今日は仕事はやめにする」「しかたなかよ。草刈り機じゃ気をつけていても、ついきってしまうもんね」と慰める。
ほんとうに百姓はおびただしい生きものの命を奪う仕事をしている。いちいち気にしていたら、身が持たない。田畑を耕せば草を枯らし、多くの生きものの生きる場を奪う。突然の代かきや中干し、落水、稲刈りにしても、生きものの命を奪う。この哀しみを婆ちゃんはしっかり受けとめて、引き受けている。私と言えば、いやその程度では絶滅することはない、それも生態系には織り込み済みで、中程度攪乱説にしたがえば、そういう百姓仕事つまり生態系の攪乱が生きものたちの遷移を止めて、安定に寄与しているのだ。その証拠に、また次の年になれば、同じように草は生え、虫は生まれるではないか、と自分に言い聞かせる。婆ちゃんに比べたら、薄っぺらな世界に住んでいる。こうした情念のふるさとと生物多様性とはどう結びつくのだろうか。
当然のことながら婆ちゃんは「生物多様性」などという考え方は知らない。しかし、生きものへの情愛は、私などよりもはるかに深い。現代人が支持する「生物多様性」は、自然という生きものの世界を外側から見ている。一方かつての日本人は、とくに百姓は、生きものを自分の世界の一員として、内側から見ていた。
友人の故・森清和の最期の言葉をよく思い出す。「自然は大好きだが、自然と言った途端に自然の外に出てしまうのが悲しい」これは自然と現代人の本質を見抜いている。明治時代の前半までは、日本人は「自然」(Nature)という言葉も概念も知らなかった。それまでは、自然はどう見えていたのだろうか。それがこの数年、ずっと気になっている。
私なりのたとえ話をしよう。池があるとする。池の中のフナには、池は見えない。ただ池の中の生きものや水や底の土、つまり池の中の世界はじつによくつかんでいた。池は、そこから岸をはい上がって、地上に出たときに見えるかもしれないが、フナはそんなことをしようとは思わない。
この池を「自然」だと思えばいい。かつての日本人は、池の中のフナであった。自然を知らなかったが、自然の中のことと十分知っていた。現代の日本人は、池を外から眺めているが、池の中に入ることが少なくなった。自然の中の生きものたちと一緒に過ごすことがなくなった。このことの不幸もまた、考えてみなければならない。「自然」を知らなかった先人たちは、私たちよりはるかに生きものを知っていた。
90歳を越える百姓への聞き取りでは、百姓は約600種の生きものの名前を呼んでいたそうだ。しかも名前を知っているだけではない。その生きものの生や自分との関係も深く身体に刻んでいる。現在では福岡県内の調査では、約150種である。科学は自然の外からの生きもの認識であるが、先人の百姓たちは自然の内側からの生きもの認識だった。現在とどう違うかと問われれば、まなざしと情愛の深さが違うと言うしかない。
子どもたちが質問してくる。「いったい、田んぼにはどれくらいの生きものがいるの」自然観、世界認識の扉を開けたがっている。それなのに「そんなこと誰も知らないよ。研究もされていないよ」では、従来の狭い科学から一歩も出られない。
私たちが百姓や子どもたちにすすめている「生きもの調査」は、世界認識の方法でもあるのだ。その方法は二つある。まず、生きものに眼を合わせて、相手の名前を呼ぶことだ。距離は一挙に縮まり、情愛が芽生えてくる。かつて、
この「情愛」を仕事の中で、百姓は深めて来た。ただの虫にも多くの地方名があるのが、その名残だ。しかし、生きものへのまなざしは、農業の近代化で衰えてしまった。そのことに農学だけでなく「科学」は冷淡だ。
科学者だけが、専門分野で種や生態を知っておけば、論文にしておけば、私たち百姓や国民のまなざしの衰退など、ほとんどどうでもいいと思っているのではないか、と疑うことがしばしばだ。ここで科学は何のためにあるのだろうか、を論じる紙幅はないので、別の機会にするが、科学が内からのまなざしを棄てたことが、この冷淡さの原因になっていることは指摘しておきたい。
そこで、科学に依拠しながらも、世界に認識へのもうひとつのアプローチが、農と自然の研究所の桐谷委員会では、2009年2月に作成した「田んぼの生きものの全種リスト」であった。これは私が科学を重視している証拠でもある。これまで「全種リスト」がなかったのは、いつのまにか科学も外側からの「世界認識」の学である使命を忘れてきたからであろう。
この世の生きもの全種に命名しようとしたリンネ(1707〜1778年)の時代には、全種とは1万種ぐらいだと思われていたそうだから、現代では途方に暮れるのもわかる。せめて個々の分野のさらに狭い種類だけにしようと言うのもわかるが、それが「世界認識」の放棄になることを科学者は少しは自覚してほしい。
日本の農地では最も研究されている田んぼの生きものの全種リストがなかったのは、科学が現代社会を支配している価値観に寄り添っていることを証明している。時代が要請しないものをやる人間は危険人物だろう。田んぼの生きものの場合は「有用性」にとらわれてきた。したがって、有用性がないものを研究対象にならなかったし、まして「世界認識」など近代化農業は歯牙にもかけなかった。
ところが、「ただの虫」という世界が見つかり、「生物多様性」が輸入され、桐谷圭治さんによって「IBM」という農学史上初めて、世界認識への切り口が提案され、生きもの調査に取り組んだ百姓や子どもたちによって、「いったい、田んぼという世界にはどれくらいの生きものが生きているのだろうか」という世界認識への志向が「全種リスト」への要請となったのである。
農と自然の研究所が桐谷圭治さんに相談して、全種リストを作成したのは「生物多様性」「IBM」という自然の外側からの概念の中身を充填するためと、「ただの虫」「ただの草」の実態を明らかにするためだ。そして何よりも「有用なもの」以外の生きものへの伝統的な百姓のまなざし復権の土台としたかったからである。
田んぼの生きもの全種リスト(桐谷圭治編)
動物 2495種
原生生物 829種
昆虫 1748種
植物 2146種
クモ・ダニなど 141種
双子葉植物 1192種
両生類・爬虫類 59種
単子葉植物 501種
魚類・ 貝類 189種
裸子植物・シダ・コケ 248種
甲殻類など 45種
菌類 205種
線虫・ミミズなど 94種
総合計 5470種
鳥類 174種
ほ乳類 45種
果たして全種を科学的に明らかにしたからと言って、ほんとうに世界認識になるのだろうか。それに、これが百姓の伝統的な生きものへのまなざしの復活にほんとうに寄与するのだろうか。何より、百姓はこの全種すべてを認識できない。科学者だってそうだろう。そうすると、だれが全種を認識するのだろうか。少なくとも人間界には誰もいないことになる。しかし「科学」では、認識できるような気になることができる。まるで「創造神」になったように。これが科学が発明した世界認識であろう。すごいと思う。だが、これだけでは困るのである。
私たちは「生物多様性」を、伝統的な文化、あるいは個人の体験で実感しているからこそ、案外違和感を抱かずに受け入れた。それは、(1)遺伝子レベルでの多様性や、(2)種レベルでの多様性や、(3)生態系レベルの多様性だけでなく、(4)情感レベルでの納得:生きものとのつきあいの経験=生きものに見とれ、生きものの死に涙する感性を土台にして、(5)文化レベルので無意識の受容:自然を外から見ることがなかった伝統的な自然観=生きものの一員だった日本人=一緒に生きてきた生きものたちへの情愛があったからであろう。
全種リストは、一つの条件付きで、その人の、その地域の、その国の生きものへのまなざしの「目録」にできる。その条件とは、この自然の外側からのリストと、自然の内側からのまなざしが出会う土俵ができるならば、という条件である。
その「土俵」の一つの実例を示してみよう。
「ただの虫」は虫見板によって、百姓によって発見された。害虫を覚え、益虫を覚えた百姓にとって、害虫でも、益虫でもない虫が気になってきたのだが、誰も知らないのだから仕方がない。「ただの虫だろう。放っておこう」と言い合っているうちに、新しい言葉と分類概念が誕生したのだ。
「ただの虫」は日本的な、生物多様性に先行した概念ではないか、という指摘はありがたいが、ただの虫は生物多様性に出会わなければ、外からの「世界認識」になることがなかった。なぜなら、ただの虫は害虫や益虫と区別する分類概念にとどまり、図のような自然の「世界認識」に育てることができなかった。ただの虫はなんのために田畑にいるのだろうか、とばかり考えてきたからだ。つまり、自然の内側からの認識の外に出ることがなかったからだ。私もこの図を書き始めた5年ほど前からただの虫はいったい何種類ぐらいだろうか、と考え始めたのだから。
今年も農と自然の研究所と環境稲作研究会合同での定例田んぼの生きもの調査で、毎月16箇所を回るが、9月になると、虫見板の上に「跳び虫」類が100〜300匹も落ちてくる。(田植直後から稲株にいることもわかった)2種が混在しているのは間違いがない。稲の枯れた下葉を食べているようだが、名前が未だにわからない、誰に聞いてもわからない。この程度にしか、田んぼのことはわかっていないのだ。
それを「わかりたい」という気持ちは、残念ながら科学的な接近からしかもたらされないようだ。しかし、科学が田んぼの跳び虫を放置しているのは、有用性がない(ほんとうはあるのに)からであるが、百姓の内側からの要請もないからでもある。つまり、百姓自身のまなざしの復活なしには、この全種リストを内と外の両側から響き合うリストにすることは不可能である。したがって、この全種リストは生きもの調査などの百姓の取組みがないところでは、科学者だけが、自分の専門領域だけを検討するデータベースになってしまうかもしれない。そうはしたくないのである。
このリストが、試験研究 田んぼの跳び虫の一種機関ではなく、農と自然の研究所という百姓たちのNPOによって作成された意味がここにある。
ここで、思想的な問題を出してみよう。二つの田んぼがあるとする。
-Aの田は赤トンボが10アールに5000匹生まれているが、当の百姓はそのことを知らない。
-Bの田では赤トンボは100匹しか生まれていないが、耕作している百姓はそのことを気にしている。 さて、どちらの田んぼが豊かだろうか。
A:赤トンボが5000匹いる しかし百姓はそれを知らない
B:赤トンボが100匹しかいない 百姓はそのことを悩んでいる
私の結論は、「Bの田がいいに決まっている」である。ところが「生物多様性」という概念を知っている人は、「Aの方が生きものが多いでしょう」と反論するだろう。それは、すでに自然を外側から見ていることに気づいていない。
私の論拠は二つある。赤トンボを見つめる百姓のまなざしがなければ、5000匹いるかどうか、誰がわかるというのだろう。次に、生きものの種類や密度だけで、生物多様性の豊かさを量ろうとするのは、科学的なようだが、大きな危険性をはらんでいる。誤解を恐れずに言えば、生きものが大切なのではなく、生きものへのまなざしが大切なのだ。赤トンボが100匹しか生まれないことを木にしている百姓は、田んぼの生きものの世界を豊に内側からみるまなざしを持っている。Bの百姓は、池の中のフナにもなりきれる人間である。
「赤トンボが飛んでいる」と妻が言う。私は「何という種類か、何匹飛んでいたか」と問う。妻は「そんなことより、赤トンボが飛んでいたのよ」と言う。つい私は、科学的に対象の種や密度に関心を注ぐ。その瞬間にそれを見つめている人間のまなざしを忘れてしまう。じつは「赤トンボが飛んでいる」という発言は、赤トンボのことだけではなく、その赤トンボ見つめる本人のまなざしや、その赤トンボが飛んでいた時と場所つまり自分もそこにいた世界全体を語ろうとしているのに、赤トンボのことにしか興味を示さない社会になろうとしているのではないだろうか。
この前ね、田んぼに行ったらね、お父さんのまわりに、ほんとうにがいっぱい赤トンボが集まって飛んでいたね。お父さんが腰を伸ばしても、ぜんぜん逃げないんだね。「そりゃあ、お父さんがイケメンだからじゃないかな」それは絶対ないと思う。「お父さんの汗の臭いが好きなんだよ」やめてよ、吐きそうになる。
「それじゃあ、お父さんの近くに来ると、何かいいことがあるからだよ」うーん、そんな気がするけど、いったい何がいいことなんだろう。
あっ、わかった。お父さんが田んぼで仕事して動き回るから、お父さんの回りの虫が飛びはねるんだね。それを赤トンボは食べに集まってくるんだね。でも、お父さん、いい気持ちだね。」
そうなんだ。百姓って、そうなんだ。
あなたにとって田んぼの生きもの調査を実施する意義は何ですか?
福岡県農のめぐみ地区 宮城県のグループ
意義 実数(人) 割合(%) 実数(人) 割合(%)
1.減農薬・有機農業の効果を確かめるため 50 29.6 19 20.7
2.農産物に付加価値をつけるため 4 2.4 15 16.3
3.環境支払いの支援金をもらうため 7 4.1 2 2.2
4.農業に対する見方や農政を変えるため 11 6.5 12 13.0
5.環境を守るため 43 25.4 −
6.地域のタカラモノさがし 5 3.0 −
7.家族や地域の子どものため 1 0.6 7 7.6
8.未来のため 6 3.6 14 15.2
9.生きものの名前や生態を知るため 15 8.9 12 13.0
10.自分の楽しみや勉強のため 6 3.6 11 12.0
11.その他 5 3.0 −
無効回答 16 9.5 −
小計 169 100.0 92 100.0
#福岡県では、一つだけ選択。宮城県では二つ選択。(2007年)
当初、私たちは「生きもの調査」を環境把握の「手段」だと位置づけようとしていた。ところが、調査自体が目的になってきたのには、驚いている。これはどうしてだろうか。「環境把握のための農業技術」が従来の技術論におさまりきれない証拠かもしれないが、「伝える」「表現する」新たな地平が開けてきているのではないだろうか。それは上のアンケート調査結果に見事に現れている。
これは私たちの体の中の二つの動機を見事に表している。私たちは9,10を土台にして、6,7,8という世界で暮らしている。そのことは、外部の人間には見えないし、説明する必要もない。しかし、それを説明しなければならない契機が生まれているからこそ、1,2,3、4という回答が出てくる。生きもの調査はこうした三層構造になっているのである。そしてもっぱら外部の人間から見ると、上層の1〜5が目立って見えるということなのである。
一番大切な世界は、9と10ではないか。これは内側からの、池の中のフナの視点であるからだ。
生物多様性に匹敵する日本的なものは存在しない。しかし、それよりももっと深い生きものへの情愛を込めたまなざしは豊かに存在してきた。こういうまなざしがないところでは生物多様性はただ自然の外側からの概念にとどまるだろう。いずれにしても科学の側から、一見科学的でない生物多様性という思想が生まれ落ちたのは、生きもの世界をとらえる科学の限界を超えようとする対案だった。そういう方向でこの考え方は育てて行きたい。一方の日本の伝統的な生きものへの情愛もずいぶん衰えてきた。このまなざしを復活させようとする試みが、「生きもの調査」であったし、今呼びかけている「生きもの語り」である。「生きもの指標」は生きもの語りのための方法でもある。
科学は人間の情感の上に咲かなければ、冷たいままだ。生物多様性もまた、私たちの生きものへの情感・情愛の土台の上に咲かせるしかない。